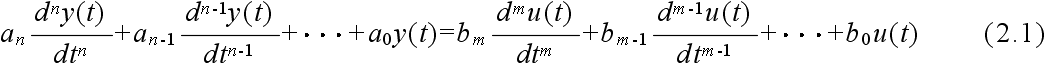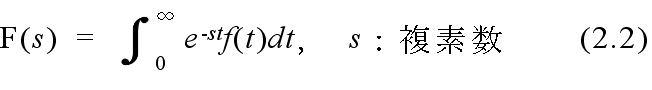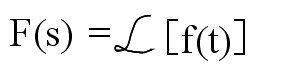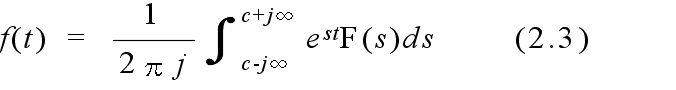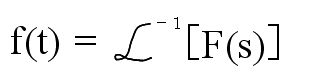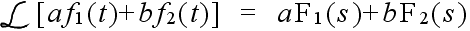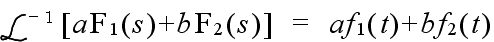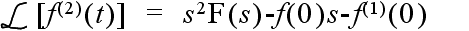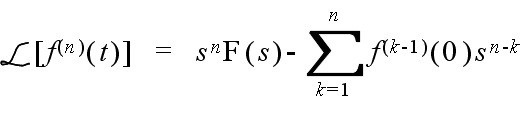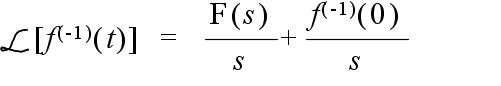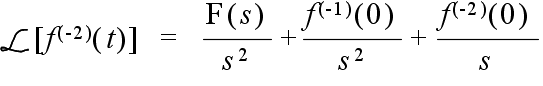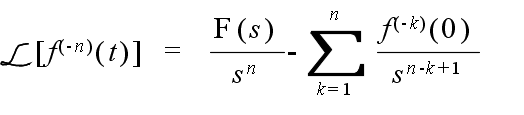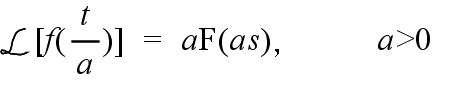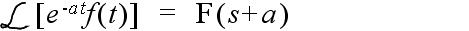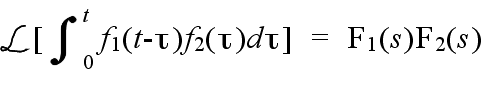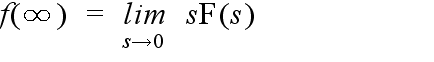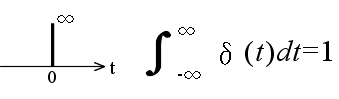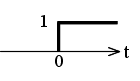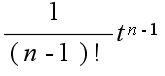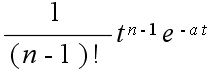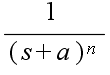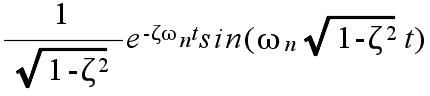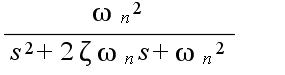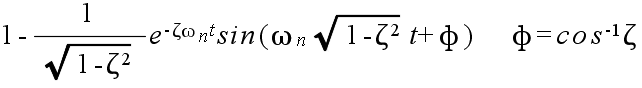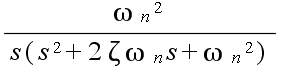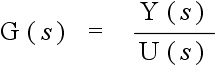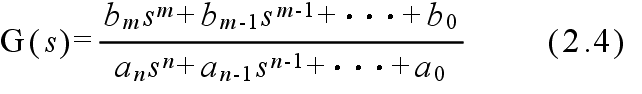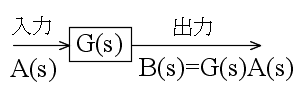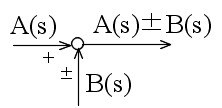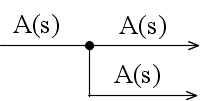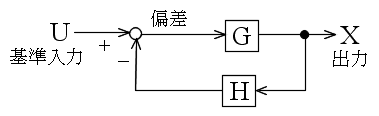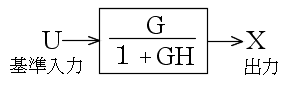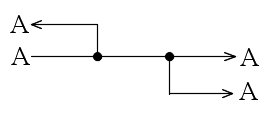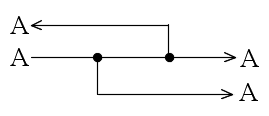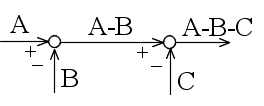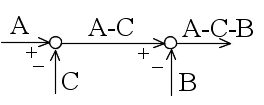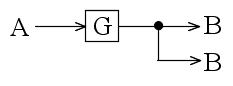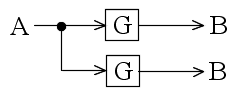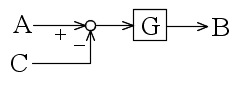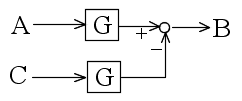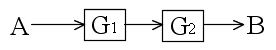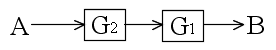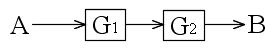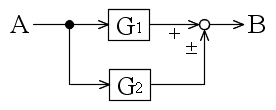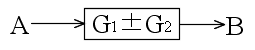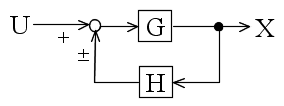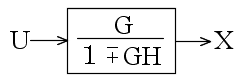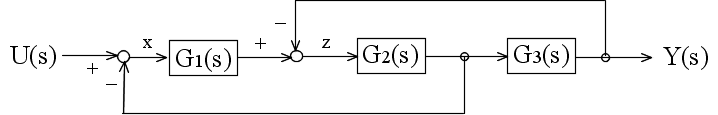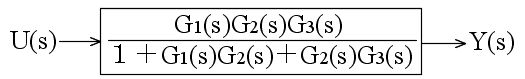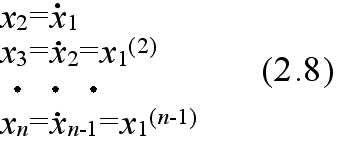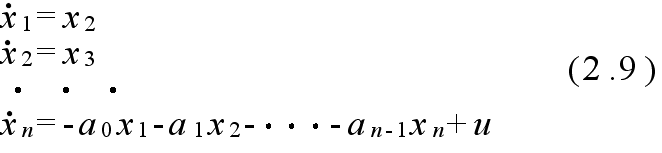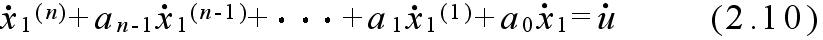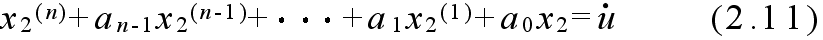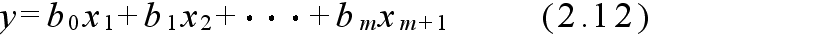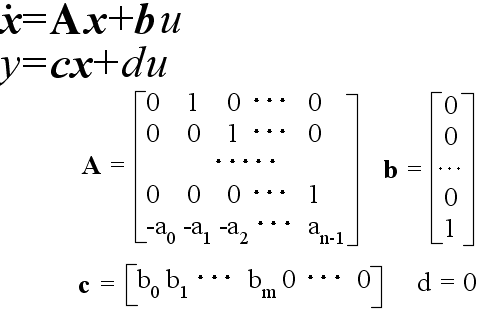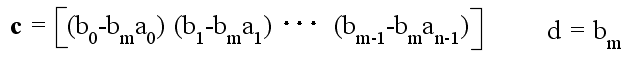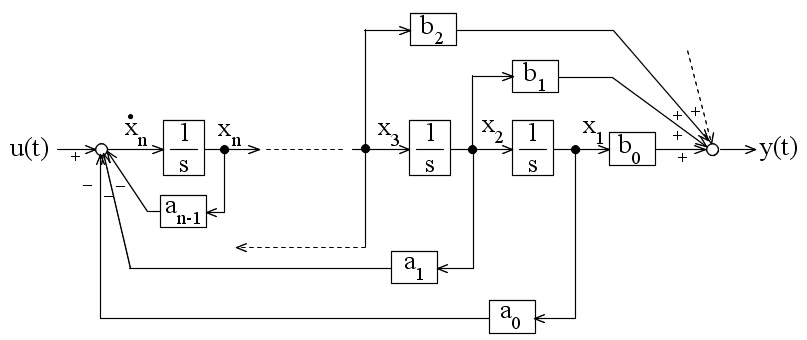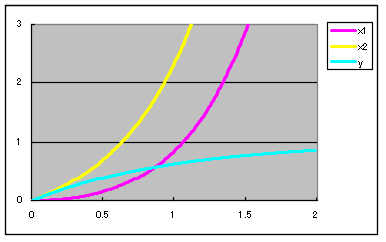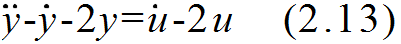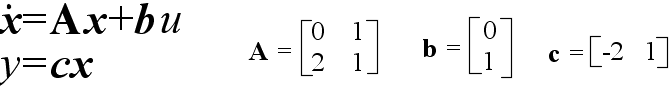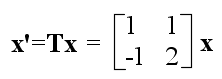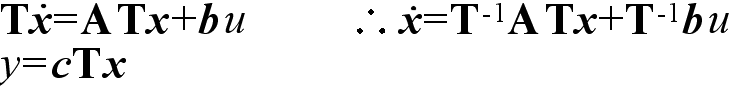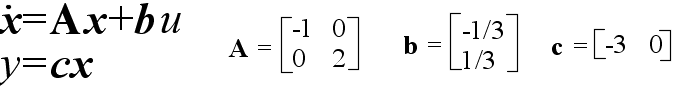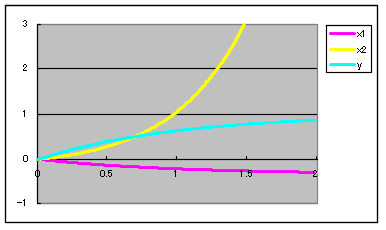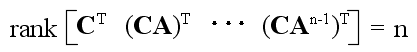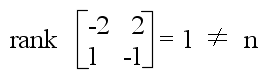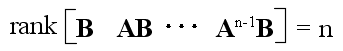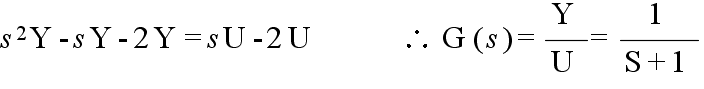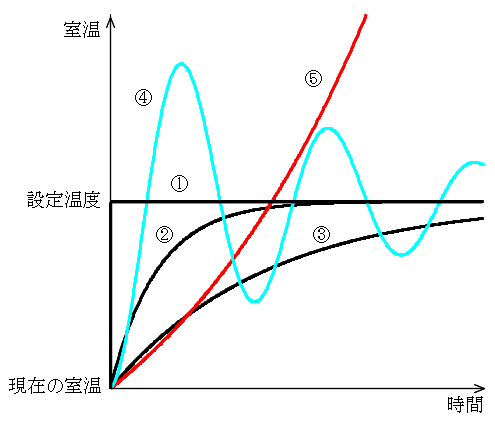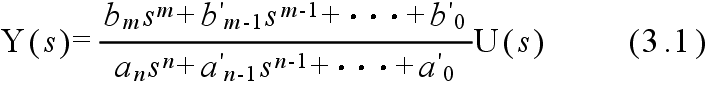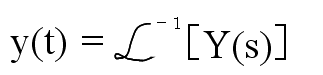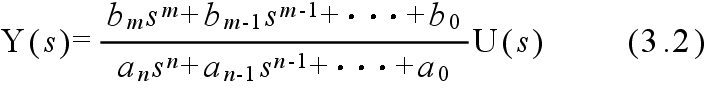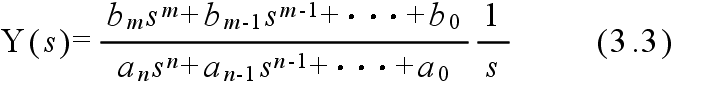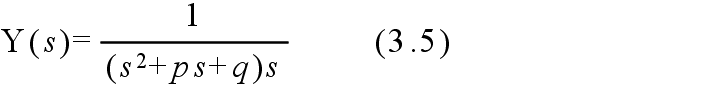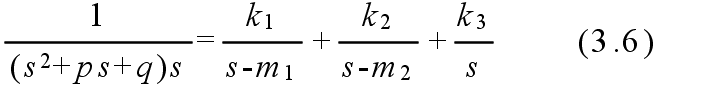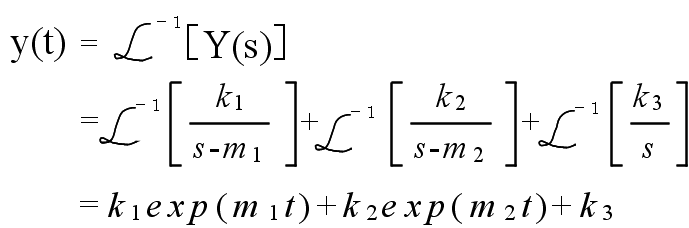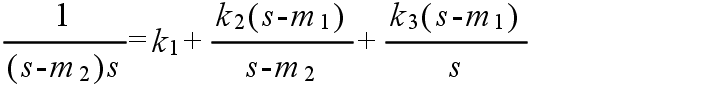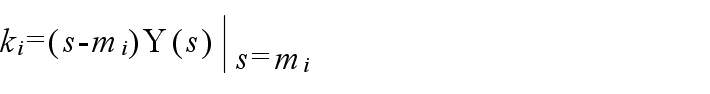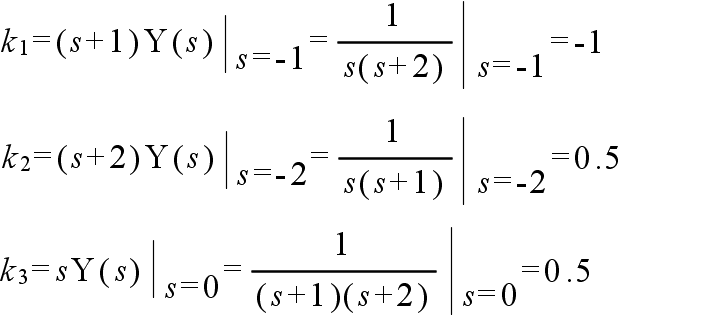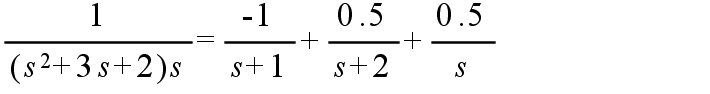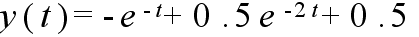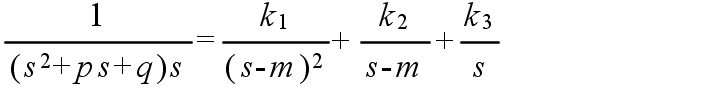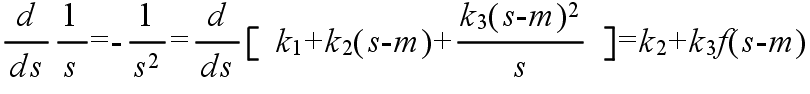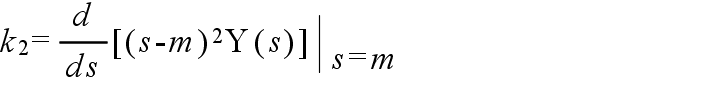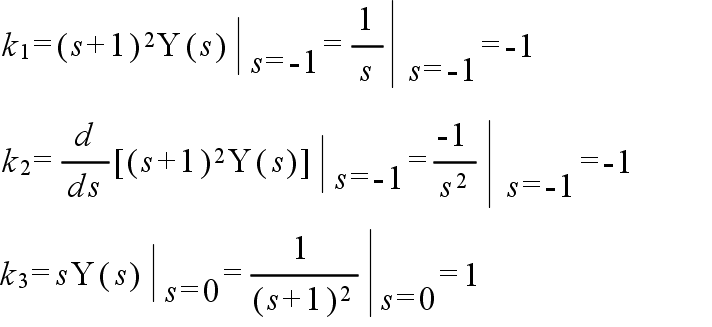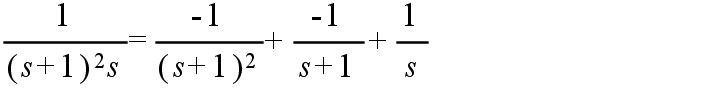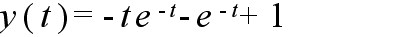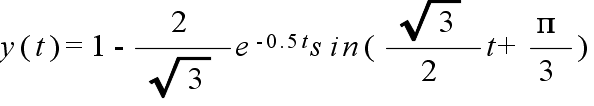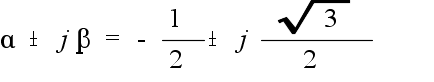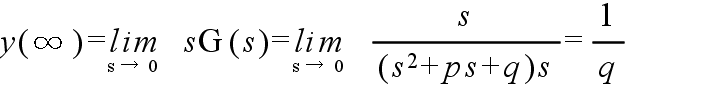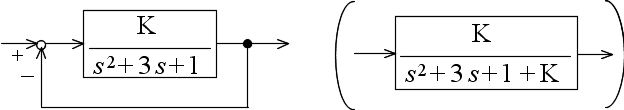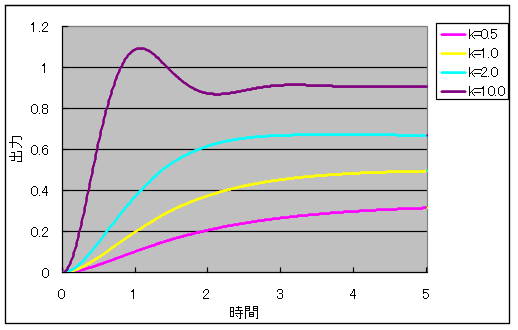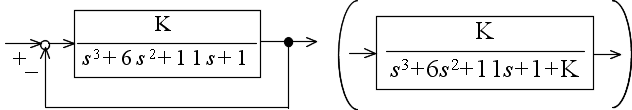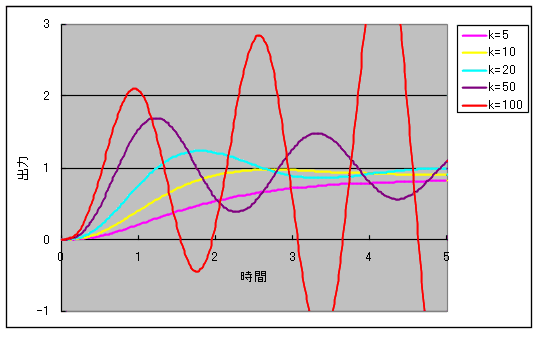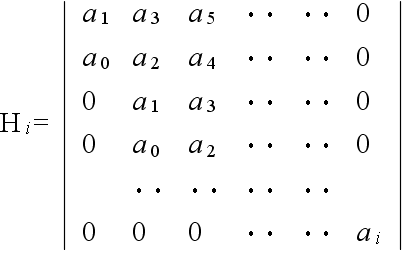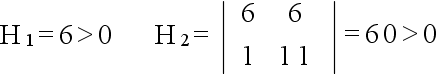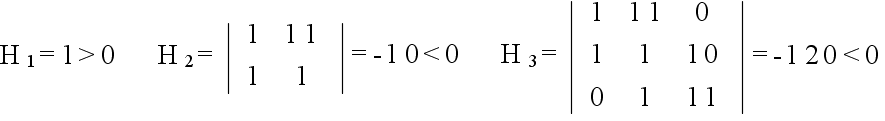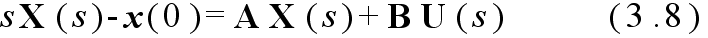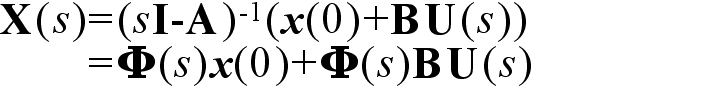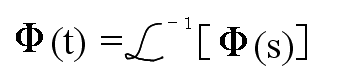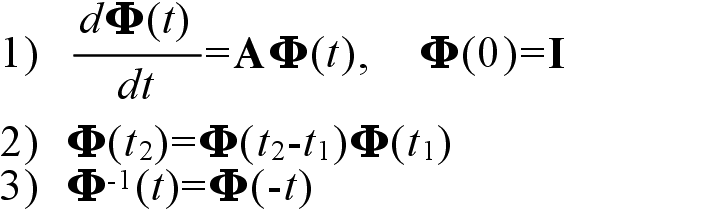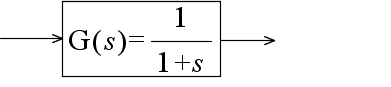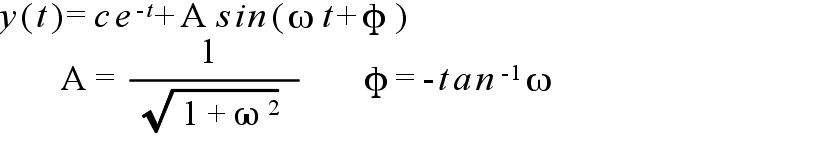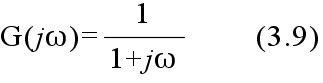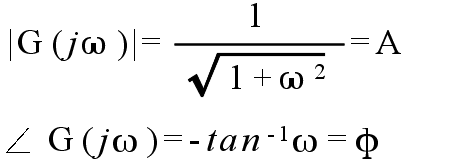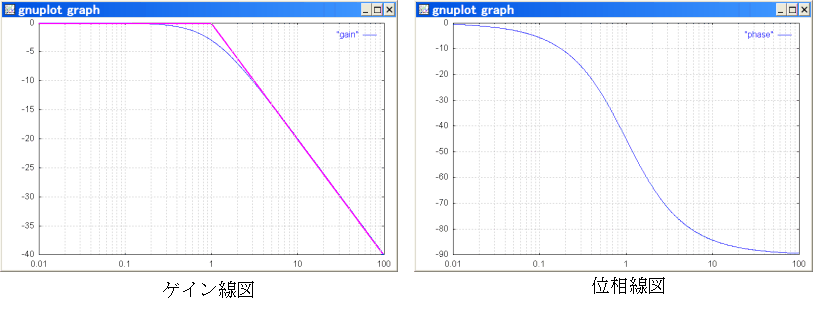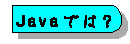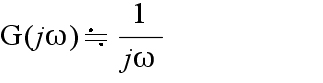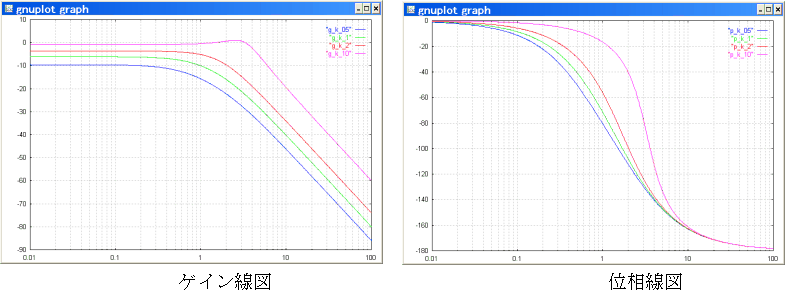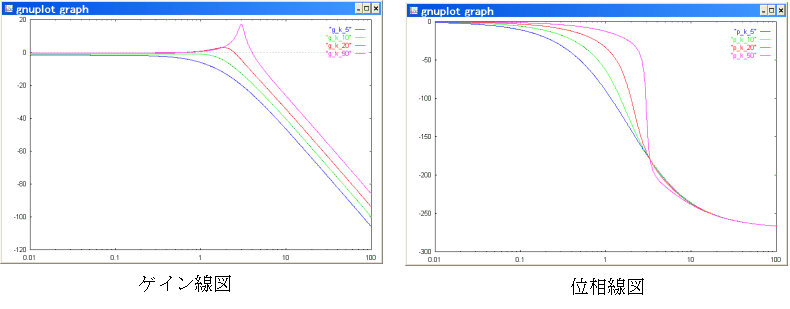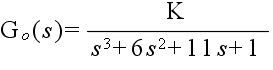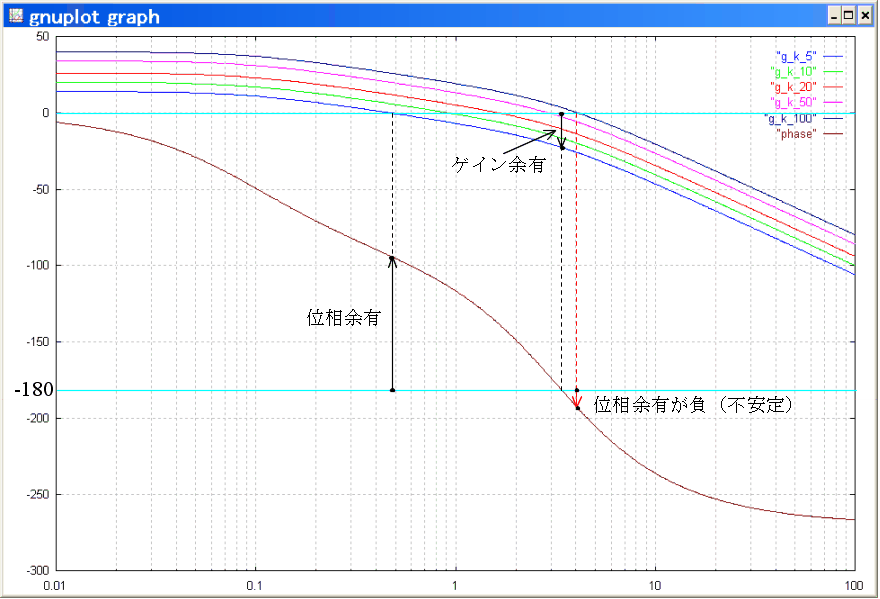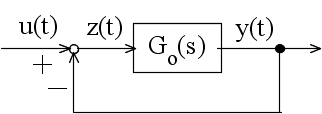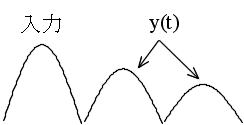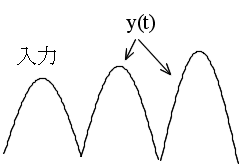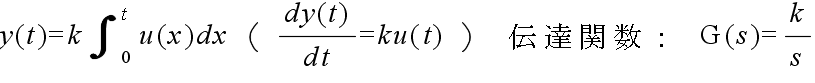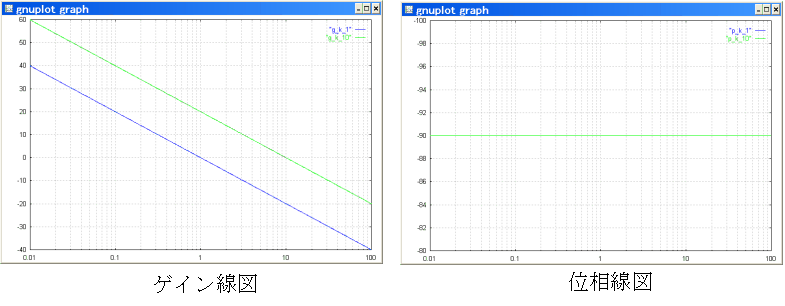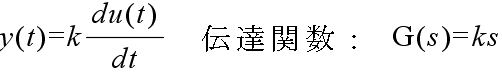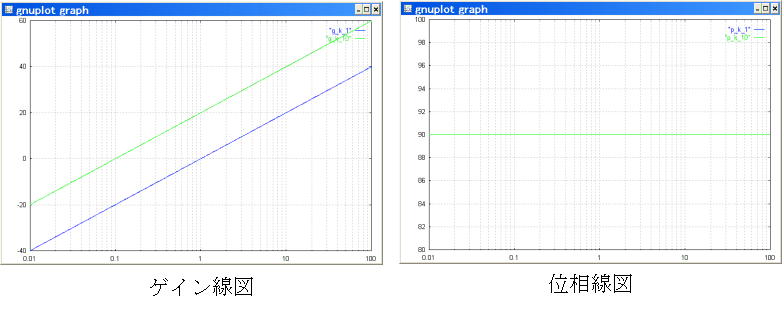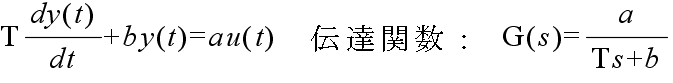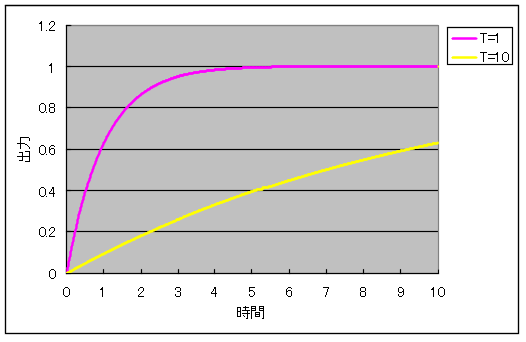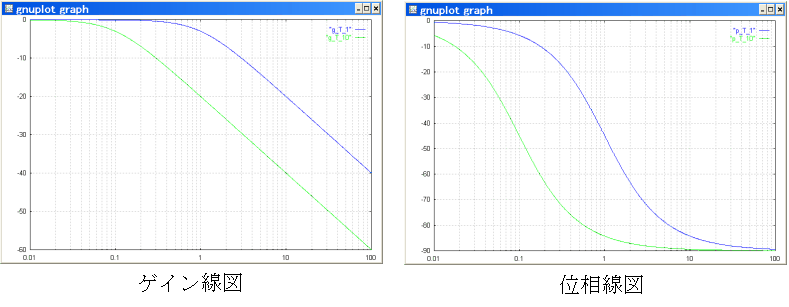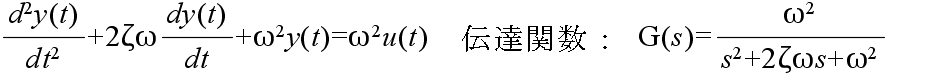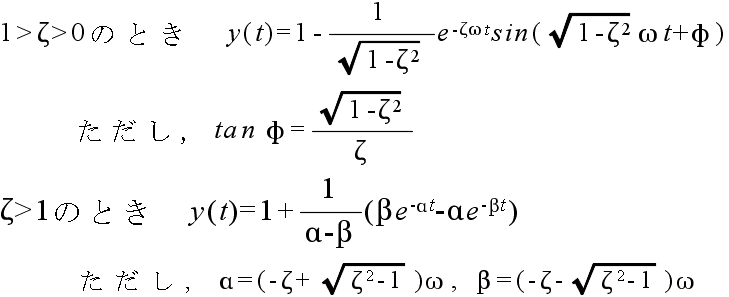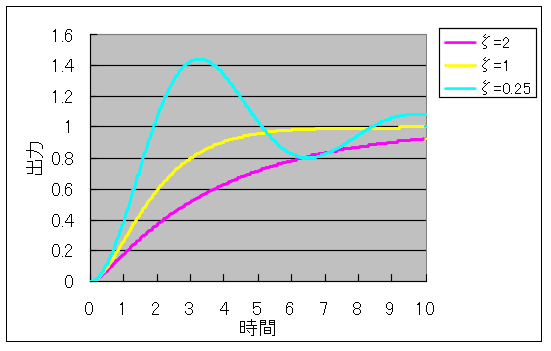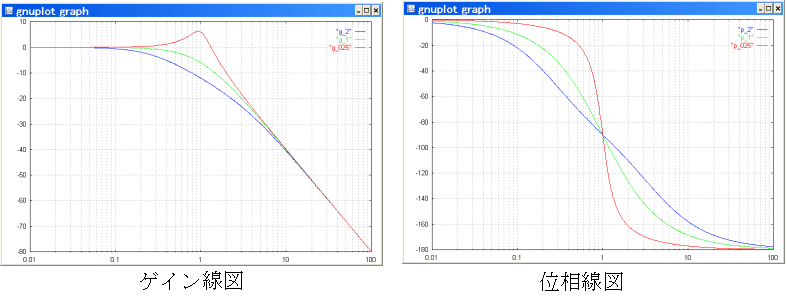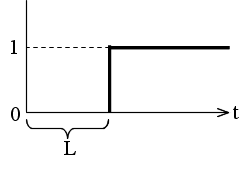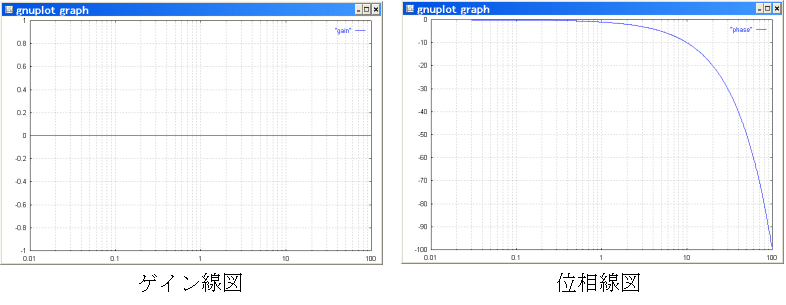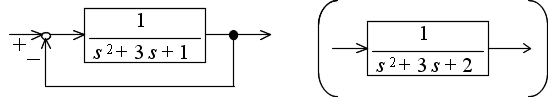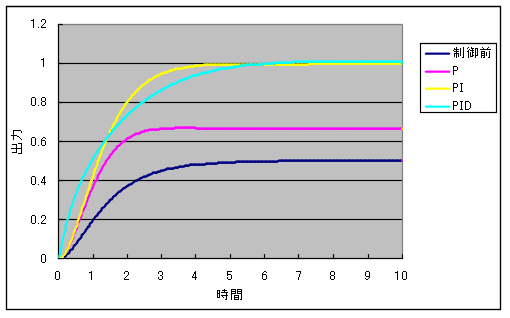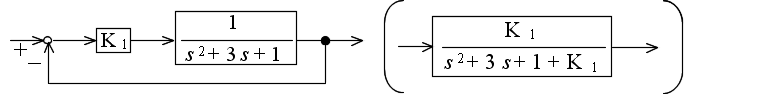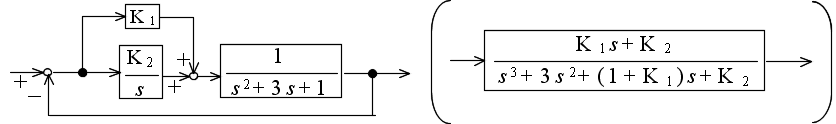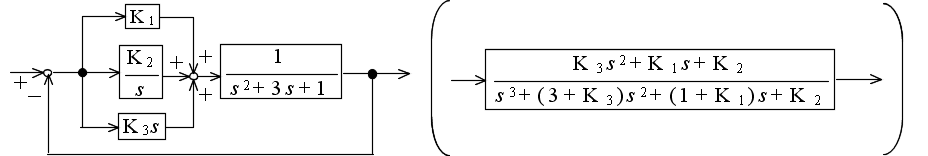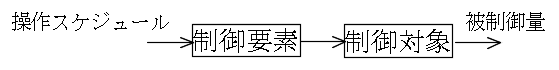
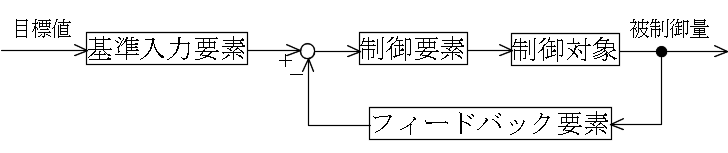
- 比例要素: 現在の出力値と目標値との間に何らかの差があれば,その差に比例した量に基づいた操作を行うのが最も簡単な方法です.しかし,差が小さすぎて測定できない,差が生じた時点で操作を行っては遅すぎる,などといった問題が生じる場合があります.
- 微分要素: 「微分積分」の章でも説明しましたように,微分とは予測演算子です.出力の変化率から,「将来は~になるであろうから,前もって,~のような操作を行っておく」といった操作が,微分要素に対応します.予測が的中すれば,非常に良い結果が得られるでしょうが,誤っていた場合は,とんでもない結果(システムが不安定になる)になる可能性もあります.
- 積分要素: 非常にわずかな水滴(誤差)であっても,それが蓄積(積分)されれば,その量は非常に多くなります.積分要素の基本動作はこの点に基づいています.しかし,この例からも明らかなように,蓄積された後に操作が行われることになりますので,操作を加えるタイミングはどうしても遅れがちになります.遅れが大きければ,システムの安定性を損なうような場合も発生します.